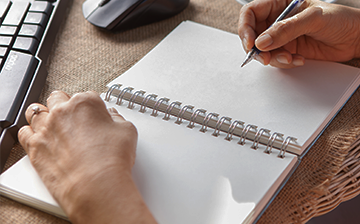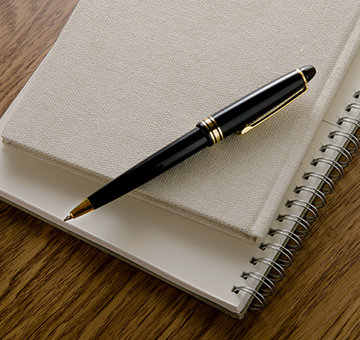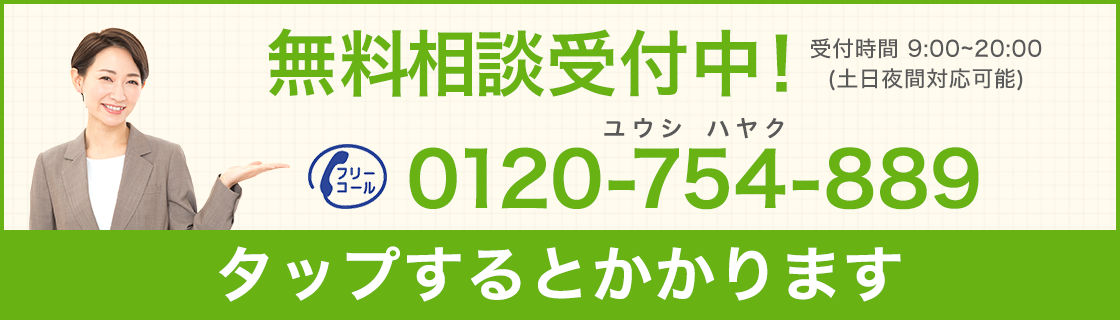眠れるお宝を呼び覚ます!「未管理著作物裁定制度」が拓く、スタートアップの新たな可能性 ~コスト削減と新規事業のチャンス~
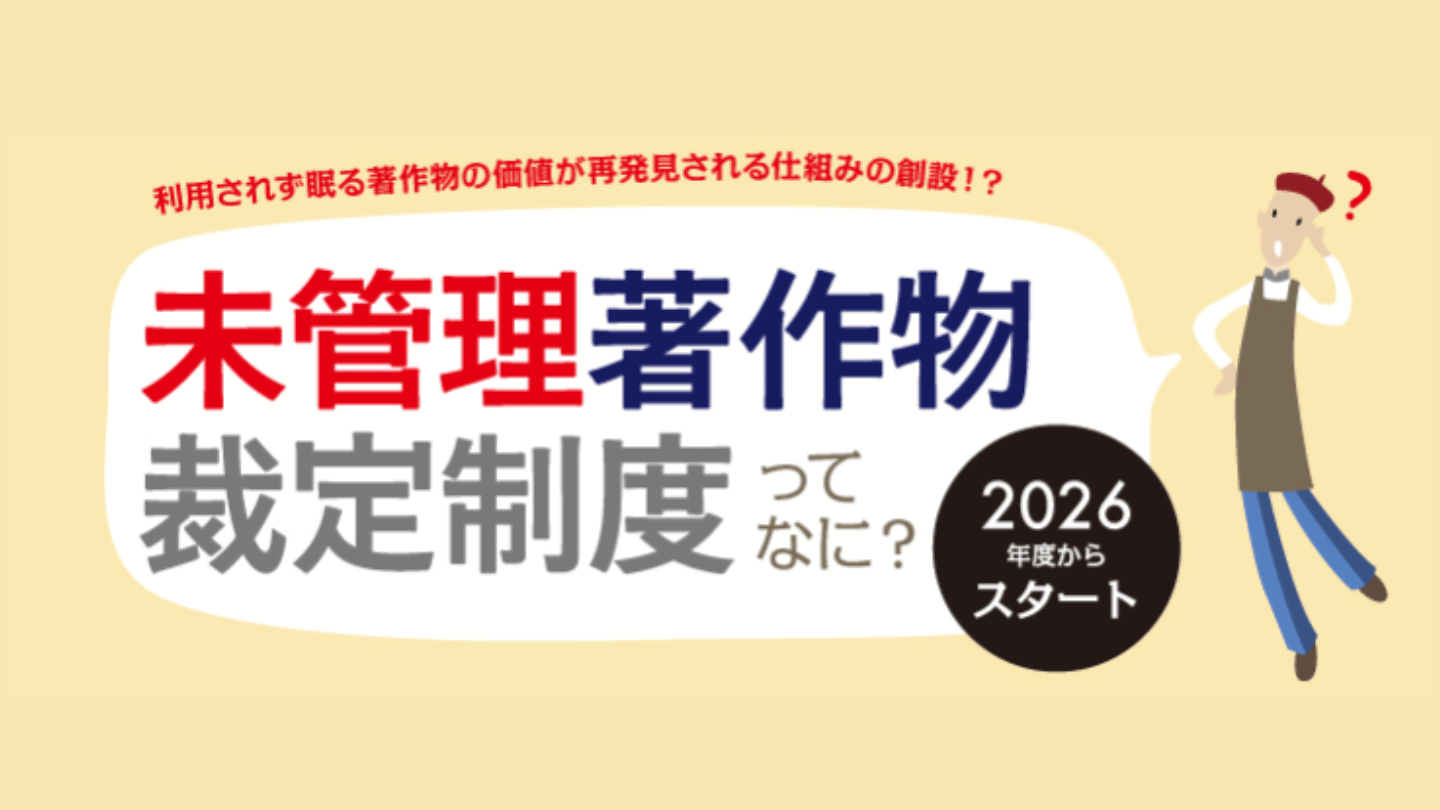
魅力的なのに作者の連絡先が分からなかったり、利用ルールが不明だったりして、使いたくても使えない…。そんな「眠っている」著作物に出会ったことはありませんか? 2026年度に施行が予定されている「未管理著作物裁定制度」は、まさにそんな「未管理著作物」を、あなたのビジネスに活用できるチャンスをもたらす新しい仕組みです。この記事を読めば、制度の基本的な内容から、あなたの会社が享受できる具体的なメリット、そして今すぐ始められる準備まで、しっかりと理解できます。特にクリエイティブ分野の創業者や経営者の方にとって、コスト削減や新しいビジネスアイデアにつながるヒントが満載です。
デジタル時代の新たなチャンス:「未管理著作物裁定制度」とは?
まず、「未管理著作物」という言葉から説明しましょう。これは、インターネット上の古いブログ記事、昔の写真、作者不明のイラストなど、著作権者はいるはずなのに連絡先がわからなかったり、どう使っていいかのルール(ライセンス)が示されていなかったりする著作物のことを指します。「孤児著作物(オーファンワークス)」と呼ばれることもあります。これまでは、こうした著作物を使いたくても、権利を持っている人に許可をもらうことが難しく、諦めざるを得ないケースが多くありました。無理に使ってしまうと、後から権利者が見つかってトラブルになるリスクもありました。
そこで登場するのが「未管理著作物裁定制度」です。この制度は、あなたが使いたい著作物の権利者を探しても見つからない、あるいは連絡しても返事がない場合に、文化庁長官に申請し、審査(=裁定)を経て、一定の補償金を預けることで、合法的にその著作物を利用できるようにする、という画期的な仕組みなのです(著作権法第67条の2)。これにより、これまで活用が難しかった膨大な数の著作物が、新たな価値を生み出す可能性を秘めています。
スタートアップこそ注目!制度活用の4つのメリット
では、この新しい制度は、特にクリエイティブ分野で新しいビジネスを立ち上げたばかりの経営者や創業者にとって、どのようなメリットがあるのでしょうか?主なポイントを4つにまとめました。
| メリットカテゴリー | 具体的なメリット例 |
|---|---|
| 1. コスト効率の向上 | 使いたい素材が見つかっても、権利者との交渉や高額なライセンス料が壁になることがありますよね。この制度を使えば、一般的な使用料に相当する補償金を支払うことで利用できるため、コンテンツ制作にかかる費用や時間を大幅に節約できる可能性があります。貴重な創業資金を、開発やマーケティングなど、他の重要な分野に回すことができます。 |
| 2. 新たなビジネスチャンス | 世の中に埋もれている未管理著作物の中には、あなたのアイデア次第で輝きを取り戻す「お宝」が眠っているかもしれません。他社が見過ごしている素材を発掘し、あなたのサービスや商品に独自性を加えることで、競争の激しい市場で差別化を図ることができます。例えば、古い記録映像を編集して新たなドキュメンタリーコンテンツを制作したり、作者不明のイラストをリデザインして商品化したり、といった展開が考えられます。 |
| 3. リスクの軽減 | 権利者が不明な著作物を利用する際の最大の懸念は、「後から権利者が出てきてトラブルになったらどうしよう…」ということではないでしょうか。この制度では、文化庁長官の裁定という「お墨付き」を得て利用するため、権利侵害のリスクを事前に低減できます。安心して事業に集中できる環境が整います。 |
| 4. 資産価値の向上 | この制度を通じて未管理著作物を活用し、それがビジネスの収益に貢献するようになれば、その利用権自体があなたの会社の「知的資産」として評価される可能性があります。目に見えない資産が増えることで、会社の企業価値向上につながるかもしれません。 |
制度利用の流れ:どうやって使うの?
実際にこの制度を利用したい場合、どのようなステップを踏むのでしょうか?文化庁の情報を参考に、大まかな流れを説明します。
- 【ステップ1】権利者を探す努力をする
まずは、利用したい著作物の権利者の連絡先や、利用に関するルールが示されていないか、「相当な努力」をもって調査します。文化庁は、この調査を支援するために「分野横断権利情報検索システム」の整備を進めており、2025年度(令和7年度)中の運用開始を目指しています。このシステムの活用も、努力義務の一環となる可能性があります。
- 【ステップ2】連絡を試みる(連絡先がわかった場合)
もし連絡先が見つかった場合は、著作物の利用許諾について連絡を取ります。
- 【ステップ3】文化庁長官へ裁定申請
ステップ1で連絡先が見つからない場合、またはステップ2で連絡したものの14日間応答がない場合(※この期間については施行までに詳細が定められる可能性があります)に、文化庁長官に必要な書類を添えて裁定の申請を行います。申請時には、権利者を探すためにどのような努力をしたかを具体的に示す必要があります。
- 【ステップ4】裁定・補償金の支払い・利用開始
文化庁長官が申請内容を審査し、利用を認める「裁定」が下りたら、定められた補償金(通常の使用料に相当する額)を法務局に供託するか、文化庁長官が指定する「指定補償金管理機関」に支払います。その後、晴れて著作物の利用を開始できます。裁定による利用期間は、原則として最長3年間です。
【大切なポイント】
- この制度は、権利者を探すための「相当な努力」を尽くすことが大前提です。安易な利用は認められません。
- 裁定を受けて利用を開始した後でも、本来の権利者が見つかった場合は、その権利者は利用の停止を求めたり、今後の利用について改めて交渉したりすることができます。その際、預けた補償金が権利者に支払われることになります。
今すぐできること:制度活用に向けた3つのアクション
「2026年度施行予定なら、まだ先の話…」と思われるかもしれませんが、このチャンスを最大限に活かすためには、今から準備を始めることが重要です。いますぐ取り組める3つのステップをご紹介します。
- 【情報収集】自社のビジネスに関連する未管理著作物を探してみる
あなたの事業分野で、「使えたら面白そうなのに、権利者が分からない…」と感じるような素材がないか、アンテナを張ってみましょう。古い業界誌、過去のイベント記録、インターネット上のアーカイブなどを探索してみるのも良いかもしれません。
並行して、文化庁の「未管理著作物裁定制度」に関する公式情報ページをブックマークし、最新情報や詳細な手続き、Q&Aなどを定期的にチェックしましょう。
- 【体制整備】社内連携と専門家への相談
社内のクリエイティブ担当者や、もし法務担当者がいれば、制度についての情報を共有し、どのような著作物が活用できそうか、リスクはないかなどを話し合ってみましょう。
早い段階で、著作権に詳しい弁護士や、知的財産に強い弁理士などの外部専門家に相談することも有効です。どのタイミングで、どのように制度を活用するのが最適か、具体的なアドバイスをもらえます。
- 【計画策定】事業計画への組み込みと申請準備
もし活用できそうな著作物の候補が見つかったら、それをどのように事業に活かすかを具体的に考え、事業計画に落とし込んでみましょう。裁定申請の手続きや補償金の支払いなども考慮に入れたフローを整理しておくと、制度開始後スムーズに行動できます。
よくある質問(FAQ)
Q1: 「未管理著作物」って、具体的にどんなものがありますか?
A1: 例えば、昔の個人ブログに掲載された写真や文章で作者と連絡が取れないもの、古い地方の出版物に載っている作者不明のイラスト、権利を持っていた会社が解散してしまい権利の行方が分からない映像など、多岐にわたります。ただし、「転載禁止」など利用ルールが明記されているものや、JASRACのような著作権等管理事業者が管理しているものは対象外です。
Q2: 「裁定」とは、具体的に何をしてくれるのですか?
A2: あなたが権利者を探す努力をしても見つからなかったり、連絡が取れなかったりした場合に、文化庁長官が、「この著作物については、一定の条件(補償金の支払いなど)のもとで利用して良いですよ」と、利用を公式に許可する決定(行政処分)のことです。
Q3: 申請すれば必ず利用できるようになりますか?
A3: いいえ、必ず利用できるとは限りません。文化庁長官が、あなたが権利者を探すために「相当な努力」をしたか、著作物の性質などを審査した上で、利用の可否を判断(裁定)します。努力が不十分と判断されれば、申請は却下されます。
Q4: 利用期間に制限はありますか?
A4: はい、現在の文化庁の情報によると、裁定による利用期間は原則として最長で3年間とされています。継続して利用したい場合は、改めて裁定申請の手続きが必要になる可能性があります。
Q5: 補償金の金額はどれくらいになりますか?
A5: その著作物の種類や利用方法などに応じて、「通常支払われるべき使用料に相当する額」を基準に、文化庁長官が決定します。具体的な算定方法については、現在文化庁で調査研究が進められており、その結果を踏まえて詳細な基準が定められる予定です。
まとめ:眠れる資産をビジネスの力に
「未管理著作物裁定制度」は、デジタル社会に埋もれたままになっている膨大な著作物という「眠れる資産」を、ビジネスの力に変える可能性を秘めた、画期的な取り組みです。
クリエイティブ分野のスタートアップや中小企業の経営者にとって、この制度は、
- コストを抑えて質の高いコンテンツを利用できる
- ユニークな素材で他社との差別化を図れる
- 権利侵害のリスクを減らして安心して事業に取り組める
- 会社の知的資産価値を高める可能性がある
といった、多くのメリットをもたらします。
2026年度の制度開始に向けて、まずはあなたのビジネスに関連しそうな「未管理著作物」がないか、探すところから始めてみませんか?そして、制度の活用を具体的に検討する際には、ぜひ著作権や知的財産に詳しい弁護士や弁理士といった専門家にご相談ください。あなたの会社の成長を加速させる、新たな一手となるかもしれません。
【次のステップへ】
- 文化庁の「未管理著作物裁定制度」公式ページをチェックする。
- 自社で活用できそうな未管理著作物の心当たりがないか、社内で話し合ってみる。
- 制度活用について、専門家への相談を検討する。
この記事が、あなたのビジネスに新しい視点と具体的なアクションをもたらすきっかけとなれば幸いです。
制度活用に向けた専門家への相談
未管理著作物裁定制度の活用した創業アイデアや事業アイデアについて、具体的なアドバイスが必要な場合は、専門家にご相談ください。当事務所では、創業者・中小企業経営者の皆さまの起業をサポートしております。
参考資料
- 文化庁. 「未管理著作物裁定制度」 *(制度の公式概要、手続き、FAQなど)*
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/chosakukensha_fumei/tyosakubutsu/index.html - 文化庁. (2024-01-29). 「分野横断権利情報検索システムの検討状況について(著作権分科会(第66回)配付資料)」 *(PDF)*
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/66/pdf/93831401_02.pdf - FREENANCE MAG. (2024-08-07). 「著作権を誰が持っているのかわからなくても著作物を利用できる!? 令和5年に著作権法が一部改正、創設された「新裁定制度」とは【弁護士が解説】」
https://freenance.net/media/legal/34446/ - 文化庁. (2024). 「未管理著作物に関する補償金額に関する調査研究(報告書)」 *(PDF)*
https://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/chosakuken/pdf/94193401_01.pdf - 世界知的所有権機関 (WIPO). (2023-10-19). 「最近の著作権政策の動向(WIPO WEBinar for WJO No.15 資料)」 *(PDF)*
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ja/wipo_webinar_wjo_2023_15/wipo_webinar_wjo_2023_15_1.pdf
*(注: 上記URLは2025年4月14日時点のものです。リンク切れや変更の可能性があります。)*
著者情報
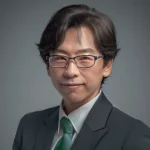
- 税理士(名古屋税理士会), 行政書士(愛知県行政書士会), 宅地建物取引士(愛知県知事), AFP(日本FP協会)
-
「税理士業はサービス業」 をモットーに、日々サービスの向上に精力的に取り組む。
趣味は、筋トレとマラソン。忙しくても週5回以上走り、週4回ジムに通うのが健康の秘訣。
最新の投稿
創業融資専門家コラムの最新記事